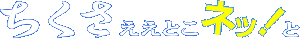全国的に少子化・高齢化が進む今日、千種町も例外ではなく、急速に過疎化が進んでいます。行政による財政や人材不足等による公共サービスの限界が見えるなか、地域課題や困りごとなど、私たちの日常的な暮らしの維持自体も難しくなってきています。
令和元年度には、千種まちづくり推進委員会・千種町連合自治会・千種市民局の三者による「三者連絡会議」を発足し、課題や困りごとの解決に取り組んでいくためにはどんなまちづくりを目指していけば良いのか、地域づくりアドバイザーを招いて議論を始めました。
◯年代・性別を問わずみんなが参加しやすいまちづくりの仕組みに変えていく
◯千種のみなさんの思いを大切にしながら一緒に進めていく
◯各種団体も含めた千種町全体をつなぐような組織をつくっていく
◯今年度一年をかけて組織の見直しをしていく
上記の4点に留意しながら、千種のみなさんと一緒に「まち推」をステップアップを図っていきます。
「生まれ変わるまち推」の第一歩として、みなさんの思いを受け止めるための「まちづくりアンケート」を計画し、その実施に向けて企画委員を募集しました。その結果、アンケート企画委員に高校生から70歳代までの7名の申し込みがありました。
アンケート企画委員会で「まちづくりアンケート」の趣旨・内容・実施方法などを検討し、千種連合自治会との連携により、12月中旬に配布、翌1月中旬に回収することが出来ました。回収率92.8%は、みなさんのご理解はもとより、自治会長・隣保長のご支援があってのことだと思います。
令和3年11月に「アンケート報告会」と題して、アンケート調査結果の報告とそれに基づく意見交換会を実施しました。千種の現状と将来、千種の将来像について、8つのグループに分かれての意見交換会でした。
この意見交換会を踏まえて、令和4年1月に「ちくさええとこ未来会議」と銘打って具体的な推進についての意見交換を行う予定でしたが、新型コロナの影響により延期となりました。
令和4年3月に「ちくさええとこ未来会議」を開催し、地域のみなさんが望む千種の将来像について、8つのテーマごとにできそうなアイデアを交換しました。それぞれのテーマについて、興味・関心のある方を募集しました。(随時、ちくさええとこセンターで受付)
①商業・観光・都市との交流
②千種高校の応援
③教育・子育て
④農業・林業・家庭菜園
⑤若い世代の移住定住
⑥自然を活かす
⑦歴史・文化を活かす
⑧趣味を活かすボランティア
ちくさええとこ未来会議の参加者や応募されたメンバーで、会合や勉強会が開かれました。
<これまで>
昨年、みなさんにご協力いただいた「千種まちづくりアンケート」を基にして、11月に「アンケート報告会」を、今年3月に「ちくさええとこ未来会議」を開催しました。延べ100名以上の方の参加を得て前向きな意見交換が行われ、千種の未来像について様々なアイデアが出されました。
ちくさええとこ未来会議では、下記の8つのテーマに分かれて話し合いました。その後のアンケート活用委員会で集約し、すでに動き始めているテーマもあります。(※印)
・商業・観光・都市との交流
・千種高校の応援※
・教育・子育て※
・農業・林業・家庭菜園※
・若い世代の移住定住※
・自然を活かす
・歴史・文化を活かす
・趣味を活かしたボランティア※
<これから>
「千種を盛り上げていきたい♡」、「こんなことしたいんやけど!」、「あんなことできへんかなぁ」など、みなさんのアイデア・ご参加をお待ちしています。一緒に楽しみましょう☆『ちくさええとこセンター』まで、お気軽にお声がけください。
今後、『第2回ちくさええとこ未来会議』の開催を予定していますので、ぜひ、ご参加ください!日程が決まり次第、チラシでお知らせします。みんなでつながりましょう☆
11月6日(日)ライブリーちくさで、2回目となる「ちくさええとこ未来会議」を開催しました。千種高校の生徒会メンバーをはじめ、一般の方や各種団体から50名あまりの参加があり大盛況でした。
最初に、昨年実施した「千種町まちづくりアンケート」から見えてきた【千種の将来像】を再確認しました。少数派である若者や社会的弱者の意見を尊重し、反映させることの大切さなどについて、アドバイザーの柏木さんからお話がありました。
また、前回の会議以降に動きのある4つのチームから、それぞれの活動を報告してもらいました。<趣味を活かすボランティア、農業・林業・家庭菜園、移住定住促進、教育・子育て・千種高校の応援>
千種高校生徒会からは、「高齢者支援プロジェクト」の発表がありました。お年寄り向けにスマートフォンやインターネットの講習会を開催して、高齢者の話し相手になろう!という嬉しい地域活性化プランです。今後の展開がとても楽しみです。
メインの意見交換会では、来場者全員が7つのテーマに分かれて話し合いました。それぞれのテーマで、「こんなことできそう!」、「できたらいいな!」、「こんな風にやればできるんじゃない?」など、様々なアイデアが飛び交いました。出てきた素晴らしいアイデアをまとめ、拠点を上手く使いながら、地域づくりに繋げていくことが大切です。テーマは分かれてはいますが、全てが繋がっていて、連携を上手く取り合いながら進めて行かねばなりません。
みんなが楽しみ、互いに助け合いながら、少しずつ【千種のまちづくり】を前進させていきましょう!
~千種まちづくり推進委員会~
平成25年3月に発足した「千種まちづくり推進委員会」は、ちょうど10年という節目を迎えました。千種町の人口は3358人から、2538人へと約800人減少(令和5年3月末)。このような状況の中で、当委員会は、千種の将来を見据えてまちづくりをステップアップさせようと取り組みを進めています。
令和3年の住民アンケートを基に、これまで「アンケート報告会」や「ちくさええとこ未来会議」などの意見交換会を行ってきました。千種の魅力や出てきた課題に対して、楽しみややり甲斐を感じられる”まちづくり”に取り組んでいくことが大切だと感じています。夏ごろに「第3回ちくさええとこ未来会議」を開催したいと考えていますので、ぜひご参加ください!
~第3回ちくさええとこ未来会議開催!~
千種まちづくり推進委員会と千種連合自治会とが連携して、令和2年度に「まちづくりアンケート」を実施しました。コロナ禍で様々なことが制限された状況でしたが、これまでにアンケート報告会や交流会、意見交換会などを重ねてきました。今回は、第3回ちくさええとこ未来会議として、高校生から80歳代まで、約60名の方が参加してくださって、意見交換も大盛況でした。
最初に、宍粟市の担当者から「宍粟市における参画と協働のまちづくりの動き」について、今年3月に策定された「参画と協働のまちづくり指針」の内容を交えながら説明がありました。現在、千種と繁盛がモデル地区としての取り組みを進めています。
その後、これまでの取り組みについてのスライドショーを見ながら、みんなで振り返りました。1回、2回と重ねた「ちくさええとこ未来会議」から生まれた活動は、少しずつですが確実に今につながってきています。千種高校生を支援する動きや農業に関すること、空き家をどうにかしたいという動きやフリマの開催といった趣味でつながる活動などを共有することにより、今後、活動が広がっていくことを望んでいます。
後半は、メインの意見交換会。参加者が8つの班に分かれて。同じテーマについてそれぞれの意見を出し合いました。意見交換のテーマは、『千種地域は、どんなまちづくりを目指すのか?』。意見交換で出された意見などは、今後、「ちくさええとこネッ!と」にアップしていきますので、そちらでご覧ください。
<今後の動き>
未来会議で出された意見をアンケート活用委員会で集約し、「まちづくり計画書」にまとめていきます。同時に<NEWまち推>の組織体制について各種団体とも連携しながら、検討を進めていきます。
年度内には、「第4回ちくさええとこ未来会議」の開催を案内させていただきたいと思います。ぜひ、ご参加ください。
「第4回ちくさええとこ未来会議」
7月6日、「千種まちづくり推進委員会総会」後に『ちくさええとこ未来会議』を開催しました。4回目となる今回は、「どうなる千種?どうする千種?千種のこれからを話そう!」と題し、高校生から80歳代まで60人以上の参加がありました。
まず、これまでの経緯や積み重ねてきた中から出てきた「千種の将来ビジョン」を発表。それを受けてメインの意見交換では、A~Gまでの7グループに分かれて、基本目標毎に取り組みのイメージについて話し合いました。アンケートや未来会議から導き出された【主要な目標】に加えて、「自分がやってみたいこと」や「既存の取組で工夫できそうなこと」、「これから新たに必要と思う取組」などを出し合い、グループ内でその優先順位を決めながら仕分けていきました。席順が抽選だったため最初は様子見でしたが、徐々に慣れてきてどもグループも積極的に対話ができていました。あっという間に時間は過ぎて、まだまだ話し足りない様子でした。
最後は、千種町連合自治会の春名会長のあいさつで締めくくられました。話の中に出てきた「私たちは今、千種にとって非常に大きな分岐点に立っている!」というフレーズが、参加者を奮い立たせました。さて、これからはみんなで楽しみながら、活動していきましょう!
<千種まちづくり計画:将来ビジョン>
「豊かな自然につつまれて、人と人があたたかくつながるまち」
ち ちくさを好きな人たちが暮らす、住んでも来ても楽しいまち
~楽しんで続けられる仕組みを取り入れよう~
く くうきを胸いっぱい深呼吸、自然と共に生きるまち
~美しい田舎風景を残そう~
さ ささえあいで生きる 違いを認め合い、良さを活かしあうまち
~大好きなちくさでつながり支え合おう~
え ええつながりで子どもを育てる 人が豊かなまち
~みんなでちくさっ子を育てよう~
え えがおあふれるちくさの暮らし みんな元気で健康なまち
~心と体の健康づくりに取り組もう~
な なかまが見つかる!誰でもチャンスに出会えるまち
~人づくりを大切にしよう~
<NEWまち推設立に向けて>
NEWまち推の組織づくりに向けて、「これからの千種のまちづくりに関する説明会」を開催し、賛同いただける各種団体代表者により、「(仮称)NEWまち推設立準備委員会」を設置しました。
7月には、第一回目となる委員会が開かれて組織体制の検討と協議が行われました。「宍粟市参画と協働のまちづくり指針」の説明や、組織体制などについて先進地域の事例を聞き、意見交換では委員からの疑問点や意見が多く出されました。この後も月1回ペースで組織体制や規約、まちづくり計画などについて協議を重ね、12月には新しい組織の設立を目指しています。
新組織の設立に伴って、年度末には「千種まちづくり推進委員会」は解散し、令和7年度より新たな「まちづくり運営組織」がスタートする予定です。
ここに暮らすうえでの危機感や千種を大切にしたいという想いに共感する仲間が集まり、その想いをみんなで共有できる「まちづくり」を目指していきましょう!
新しい千種のまちづくり仕組みづくり 大詰めデス
(仮称)NEWまち推の設立に向けて!
千種町が4町合併し宍粟市になって今年で20年になります。この間、千種地域のまちづくりを考え、実行していく体制が、多くの方々のご努力で作られ実行されてきました。そして、今の「千種まちづくり推進委員会」につながっています。
そこで、もう一度、千種のまちづくりについて、全町民の意見を聞き、全町民のまちづくり組織として再スタートするべく、まず、2020年に全町民の皆さんにまちづくりアンケートをとらせていただきました。その後、コロナ禍もありましたが、何度も何度も会合をしていただき、いよいよ千種町の自治・まちづくりの新しい仕組みを2025年度からスタートさせるべく、大詰めの段階になってまいりました。
<今後の予定>
1月29日に第6回(最終)設立準備委員会
このようなまちづくりの原案をもとに、第6回設立準備委員会をします。
ここで、いよいよこの原案の最終決定、また、この会の正式名称の決定等をしていきます。
2月24日に設立総会を開催することを決定しました
設立総会では、市長をはじめとする来賓参加のもとで、多くの地域の皆さんにお集まりいただき、規約、組織体制、役員体制、千種まちづくり計画などを決定していけるよう準備を進めています。
又、設立総会のあとには、今回で、第5回目となる「ちくさええとこ未来会議」の開催を計画しています。未来会議は、年齢や性別、自治会などの枠を越えて、自由に意見交換ができる開かれた場として定着してきました。ご近所・ご友人などお誘いあわせの上、多く皆さんに参加いただきたいと思っています。詳細については、2月広報とともに配布予定の案内チラシをご確認ください。
この「ええとこ通信」も「千種まちづくり推進委員会」発行は今号が最後となります。次号からは、新しい組織名での発行となります。
旧4町が合併して20年。宍粟市の北西の端に位置する千種町が宍粟市に埋もれてしまうことなく、いつまでも千種町としての地域コミュニティ、地域のつながり、地域の求心力を維持していくために、待望の「千種のことは千種町民が決めていき、自分たちで行動していく」仕組みがバージョンアップし、再スタートします。
仕組みや規約など、宍粟市内だけでなく、他地域を見てもなかなか見当たらないような素晴らしい案を考えていただきました。今後、市内他地域のモデルとなればと願っています。とは言え、実際に活動を始めると、修正した方がよいところは多々出てくるでしょうから、それは、その都度修正し、より実態に合ったよりよい仕組みをみんなで作っていければよいのではと思います。
これから、ますます人口が減っていきますが、だからこそ、みんなバラバラでなく、できるだけ助け合う暮らし、心を寄せ合う暮らしができればと思います。そのための仕組み作りはとても大切です。
無理のないところで、自分の関われるところから、何かお互いに役に立つ、助け合うことを、楽しくやっていければと思います。